エンジニアリングレジンで光造形が「当たり前」の手段になる――プロダクトデザイナー/新工芸家、三田地博史の3Dプリンタ活用術
- Admin
- 2019年11月9日
- 読了時間: 5分
更新日:2022年3月2日

3D プリンタは産業用途の試作だけでなく、デザイナーやアーティストの表現活動にも利用されています。京都で活躍する三田地博史さんもそのひとり。フリーのプロダクトデザイナー/現代の新しい工芸家として3Dプリンタによる表現を追求しながら、量産品の開発にもフル活用しています。場面に応じて3Dプリンタの方式や素材を使い分ける、三田地さんの活動について伺いました。

三田地博史(みたちひろし)(twitter)
プロダクトデザイナー/新工芸家。株式会社YOKOITOデザイン責任者。
京都工芸繊維大学/大学院でデザインを学んだ後、株式会社キーエンスで製品デザイン業務に従事。現在は株式会社YOKOITOでデジタルファブリケーションを中心とした研究活動・自社商品開発を行い、フリーランスデザイナーとしてもデザイン業務を請負う。

三田地さんの近作「Tilde」シリーズは、FDM(熱溶解積層)方式の3Dプリンタを用いて出力された、プラスチックでありながらテキスタイルのような織りの質感を持つプロダクトです。これまでネガティブに捉えられていた3Dプリンタの積層痕を技術レベルで捉え直し、むしろ見せるものとすることで造形時間の短縮と生産性の向上、さらには温かみのある質感を実現しました。
3Dプリント技術をひとつの表現まで落とし込んだ三田地さん。デザインを学んでいた学生時代から3Dプリンタに親しんでいたのでしょうか。
三田地「学部生の頃は手でスタイロフォームや木を削っていました。機械工学科にハイエンドな3Dプリンタがあったのですが、ほとんど触れる機会はなかったんです。大学院一回生のとき、コンペの賞金で3Dプリンタを組み立てるワークショップに参加してから製作に使うようになりました。まだ学校には導入されていなかったので、他の学生からもプリントを依頼される出力センターみたいになっていましたね」

大学院修了後、キーエンスに入社。プロダクト・UI・グラフィックと一通りのデザイン業務を任され、他部署からの依頼に短期間で答え続ける「筋トレ」のような日々が続いたといいます。
三田地「部署にあったキーエンスの業務用3Dプリンタを使い倒していました。コストも気にせずバンバン出して、とにかく短いスパンで試作を重ねて他部署を満足させる。3Dプリンタで試作を繰り返すワークフローを習得できました」
学びが多い一方で、とにかく忙しい仕事だったと語る三田地さん。キーエンスを退職後、学生時代から3Dプリンタを通じてつながりのあったYOKOITOに転職します。販促グッズやWeb、展示設計などのデザイン業務全般を手掛けながら、光造形を用いたオリジナルの製品開発に取り組みました。


三田地さんがYOKOITOで手がけた製品が、ウェアラブル送風機「SoFuu」です。3Dプリントから組み立て、パッケージングまですべて社内で行っていることが特徴で、本体の外装にはformlabsのエンジニアリングレジン「Durable」が用いられています。
三田地「『SoFuu』はクリップのように挟んで使えるようにしたいと思いました。最初はDurable以外の素材を利用していたのですが、ちょっと使ったり落としたりすると割れてしまったんです。Durableは落としても割れないし、衣服にクリップするための靭性もあるので、ウェアラブルな『SoFuu』の素材として適切でした」


「SoFuu」の開発で学んだノウハウは個人製作にも反映され、「Tilde」シリーズのシャープペンシルではノック部分にDurableレジンが用いられています。
三田地「Durableは少しなら無理に押し込んでも割れないから安心感があるんです。精度が必要な機械的部品は光造形でプリントして、FDMで出力した体積の大きな部分と組み合わせるのはちょうど良い使い方だと思います」


「Tilde」シリーズにはシャープペンシルや小物入れ、照明のシェードなどのバリエーションがありますが、いずれもFDM方式の3Dプリンタで製作されています。その一方で、三田地さんはプロダクトの試作用途にFDMを使うことはなく、プロトタイピングや外から見えない構造部品の出力にはDraftレジンを使用するといいます。

三田地「キーエンス時代から光造形機を使った試作が当たり前でした。低価格なFDM方式プリンタで試作しても本来の設計寸法通りに組みあがることはないので、サポート材のことも考慮した「FDM専用の設計」が必要になり、結局手間がかかってしまいます。射出成型品の仕上がりもイメージできないので、FDMと光造形での試作はまったくの別物だと考えています。
Draftは光造形でも印刷時間がとにかく早いし、面が反るようなトラブルもない。Form WashとForm Cureを使った後処理は必須ですが、とにかく失敗しないですね。0.3mmピッチの積層痕が出るので、そのまま納品することはありませんが、時間に追われているときの試作では本当に重宝しています」


京都の地蔵盆祭りのために制作した「ミンミンDJ」は、シーケンサーに配置したセミの鳴き声でDJプレイができるデバイス。セミはStandardを着色したもの、内部の電子部品を固定する治具にはDraft、と用途に応じてレジンを使い分けています。
三田地「内側の治具が16セット必要なのにあと2日もないぞ!という状態から、何とかフル稼働して間に合わせることができました。他のレジンでは一日1回が限界でも、Draftなら2~3回出力できるチャンスがあるので、日々締め切りに追い詰められている僕にとっては感動ものです(笑)」

耐久性があり実用に耐えるDurable、とにかく早くプリントできるDraft。光造形機のエンジニアリングレジンを普段使いの素材として使いこなす一方で、FDM方式のプリンタをハックしながら新しい表現を開拓する三田地さん。目的に合わせて3Dプリンタや素材を使い分けながら、プロダクトデザイナーや新しい工芸家としての活動を続けています。
(取材・執筆)淺野義弘(Link)
Formlabs公式 エンジニアリングレジンウェビナー開催のお知らせ(11/18・11/20・11/22)
Formlabs Japan主催でエンジニアリングレジンについての公式オンラインセミナーが開催されます。この機にぜひご参加ください。
エンジニアリングレジンのご紹介は以下から



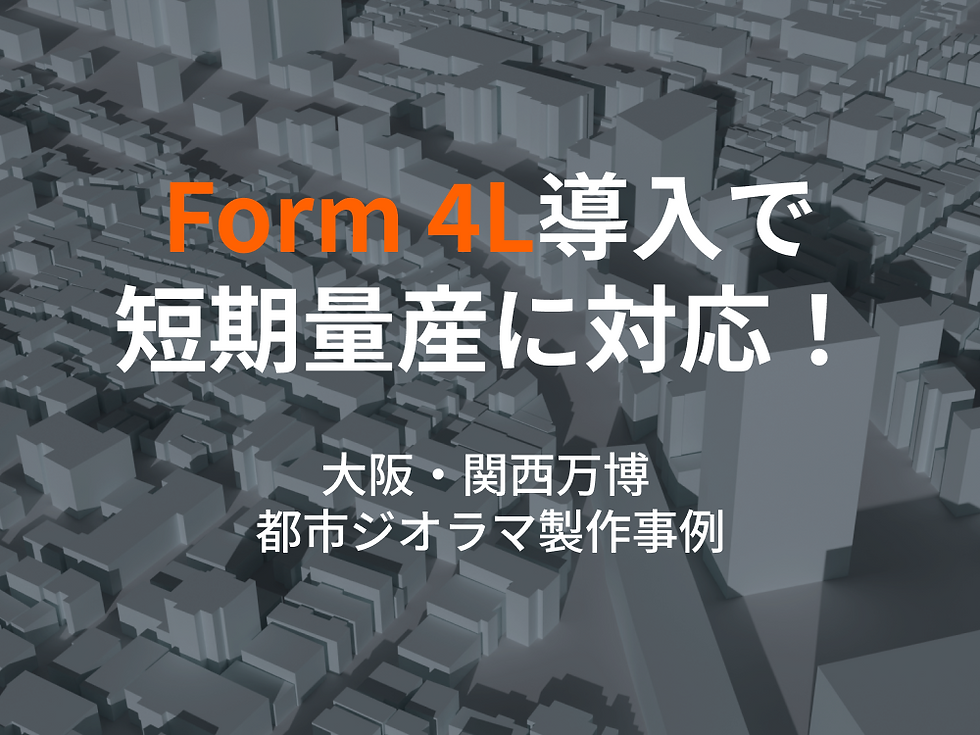


コメント